法的再生 と 私的再生 の違いとは
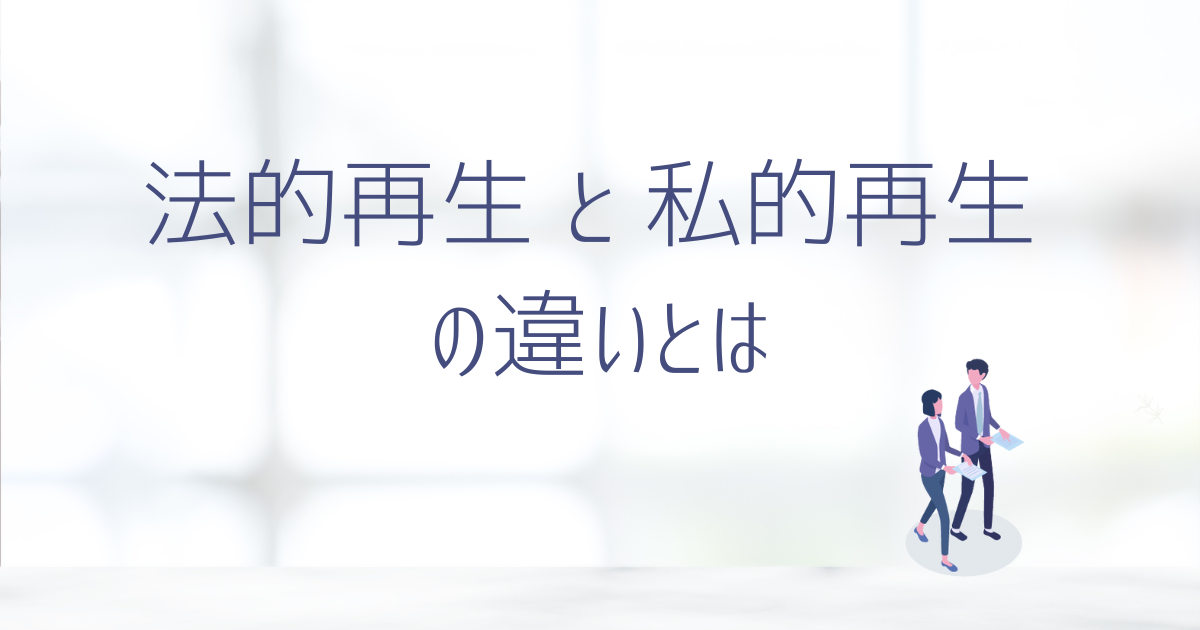
企業が経営困難や債務超過に直面した場合、法的な手続きや交渉を通じて再建を図る「法的再生」と、債権者との協力や合意に基づく「私的再生」という2つの選択肢が考えられます。どちらの手法を選ぶべきかについては、企業の状況や目標、債務の性質などによって異なります。
本記事では、企業の「法的再生」と「私的再生」の違いについて詳しく解説し、それぞれの手法の特徴やメリット・デメリットについて考察します。
現在、新型コロナ感染拡大や物価高騰などの影響で、経営状況が悪化している企業様も多いのではありませんか?そのような状況で、企業再生などを模索する経営者や関係者の皆さまにとって、より適正な判断をするための参考となる情報をお届けいたします。
法的再生と私的再生の違いとは?
企業の法的再生と私的再生は、それぞれ異なる手法であり、メリット・デメリットが存在します。事業再生を検討する際には、具体的な状況や債務の状態に応じて最適な手法を選択することが重要なため、専門家にアドバイスを受けることを検討しましょう。
1)法的再生とは
民事再生法などの手法を用いて行われる事業再生の手段で、裁判所の関与を受けながら再建を図る手続きです。裁判所が公正中立な立場から判断し、債権者の権益を保護しながら再生を進めます。この手法では、裁判所が介入するために手続きが複雑になりますが、不正行為の防止や公平性の確保が期待できます。
2)私的再生とは
債務者と債権者との間で話し合いを行いながら進められる事業再生の手法で、裁判所の関与はなく、自主的な合意によって再生を目指します。私的再生では、債権者の同意を得ることが重要であり、債務の減免や支払条件の変更などが行われます。この手法では、柔軟な対応が可能であり、債権者との信頼関係を築くことが重要です。
3)事業再生の検討について
企業の事業再生を検討する際には、まず私的再生を検討し、法的再生は最終手段として考えることが一般的です。私的再生では、債権者との合意が得られれば債務の大幅な減免が可能であり、事業の再建を円滑に進めることができます。一方、法的再生では裁判所が介入するため手続きが複雑になりますが、公正中立な判断が下され、債権者の権益を保護できます。
法的再生の種類
法的再生には、清算型(破産型)と再生型の2パターンがありますので、企業の状況に応じて適切な手法を選択することが重要です。
1)清算型(破産型)
清算型は、事業を畳むこと(破産・清算)を目的としています。経営状況が回復不可能である場合や債務超過がある場合に採用されます。この手法では、裁判所の管理下で会社の資産を売却し、債権者に対する債務の返済を行います。会社は解散し、その後は清算手続きが進められます。
2)再生型
再生型は、事業を再建し、持続可能な経営を目指すことを目的としています。経営状況が一時的な困難に陥っているだけの場合や、事業の再生が可能である場合に適用されます。再生型の手法には、「民事再生・会社更生・特定調停」などがあります。
| 民事再生 | 会社更生 | 特定調停 |
|---|---|---|
| 民事再生は、裁判所の監督の下で、債務免除や支払い条件の変更を行い事業の再建を図ります。会社の経営陣はそのまま残ることができます。 | 会社更生は、裁判所の監督の下で、会社の経営再建を行い債権者との交渉を通じて債務の免除や支払い条件の変更を実現しますが、経営陣の交代が求められます。 | 特定調停は、簡易裁判所の仲裁の下で債権者との和解を目指し、事業再生を図ります。 |
私的再生の種類
企業の私的再生は、経営状況が悪化した企業が柔軟かつ迅速に再建を図る手法です。私的整理ガイドラインの活用や事業再生ADR、中小企業再生支援スキームなどの手法を適切に活用することで、企業の再建を成功させることができます。債権者との話し合いが成功すれば、経営状況の悪化に悩む企業経営者にとって、非常に有効な方法となるでしょう。
1)私的整理ガイドライン
このガイドラインは、経営者や関係者が参考にしながら再建計画を策定するための指針となります。資金繰り改善や債務の再編成などの具体的な手法が示されており、経営者はこれを活用して再建の方針を決定できます。
2)事業再生ADR
事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)は、私的再生を進める上で重要な手法の1つです。ADRは、紛争解決手続きの一種であり、経営者(債務者)と債権者との間で合意を形成するための場として活用されます。債権者との協議を通じて、債務の繰り延べや減免、支払い条件の見直しなどを行うことができます。事業再生ADRは、裁判所の介入を必要とせず、迅速な再建を実現するための有効な手法とされています。
3)中小企業再生支援スキーム
中小企業再生支援スキームは、中小企業の事業再生を支援するための仕組みで、金融機関や専門家と連携して、企業の経営改善や財務支援を行います。
中小企業再生支援スキームでは、企業の現状分析や再建計画の策定、資金調達の支援などを行い、経営者が再建に向けた具体的な施策を実行できます。このような支援制度の存在は、私的再生を進める上で大きな支えとなります。
法的再生のメリット・デメリット
企業は自身の状況や課題を考慮し、法的再生を選択するかどうかを慎重に判断する必要があります。経営の持続性や成長性を考えながら、最適な再生策を選択することが重要です。
1)法的再生のメリット
基本的に、法的再生は企業の存続を可能にする手段です。経営の危機に直面している企業が法的再生を選択することで、債務の減額や再建計画の策定などを行い、事業を継続できます。
また、企業は債務の返済条件をリスケジュール等できます。例えば、債権者との交渉によって借入金の返済期間を延長したり金利を引き下げたりでき、これによって企業は負担を軽減し、経営の立て直しを図ることができます。
さらに、企業の信用を回復させる効果もあり、経営危機に陥った企業が法的再生を成功させることで、債権者や取引先からの信頼を取り戻すことができます。信用回復によって、新たな資金調達や取引の機会が広がり、企業の再生を促進できます。
2)法的再生のデメリット
法的再生手続きは時間と費用がかかることがあり、債務整理や再建計画の策定、債権者との交渉など、多くの手続きが必要となります。そのため、手続きの遅延や追加費用の発生が起こる可能性があります。
また、企業の経営権や株主の権利にも影響を与えることがあります。債務の減額や再建計画の策定に伴い、経営陣の刷新や株主の持分割当てが行われることがあり、経営陣や株主の意向が反映されず、経営のコントロールが制限される可能性があります。
さらに、企業のイメージやブランド価値にも影響を与えることがあります。経営危機に陥った企業が法的再生を行うことで、その事実が公になる場合があり、取引先や顧客からの信頼や評価が低下する可能性があります。
私的再生のメリット・デメリット
私的再生は柔軟性や迅速性などのメリットがありますが、関係者の協力や計画の実行に課題がある点に注意が必要です。
1)私的再生のメリット
まず、私的再生は柔軟性があります。法的拘束力がないため、会社の再建計画を自由に立てることができます。関係者同士の合意に基づいて進めるため、裁判所の判断に頼る必要がありません。
また、迅速な対応が可能です。手続きが比較的簡易であり、裁判所の審査や手続きの時間を省くことができます。そのため、事業再建を迅速に実現できます。
さらに、経営者の意思決定の自由度が高まります。経営者が主体的に再建計画を策定し、関係者と協議でき、経営者の意思に基づいた再建策を実現できます。
2)私的再生のデメリット
まず、関係者間の合意が必要です。私的再生は関係者同士の合意に基づいて進められるため、関係者が協力する必要があります。関係者間の意見の相違や対立が生じる場合、再建計画の策定や実行が難しくなる可能性があります。
また、法的拘束力がないため、約束が守られる保証がありません。裁判所の監督がないため、関係者が再建計画や協議内容を守る義務が法的に強制されません。そのため、関係者の協力や計画の実行が順調に進まない可能性があります。
法的再生と私的再生の選択基準
企業の経営危機においては、具体的な状況や債権者との関係性によって最適な手法が異なるため、専門家の助言を受けながら慎重に判断することが重要です。事業再生を成功させるためには、適切な手法を選択し、債権者との協力関係を築くことが欠かせません。
1)企業の状況と目標による選択
企業が事業再生を検討する際には、まず自身の状況と目標を考慮する必要があります。法的再生は、裁判所の管理下で行われる手続きであり、手続きの過程で企業の経営権が制限される可能性があります。
一方、私的再生は、債権者との話し合いによって進められる手法であり、企業の経営権を保持しながら再建を図ることができます。したがって、企業が経営権を重視し、自主的に再建を進めたい場合には、私的再生を選択することが適しています。
2)債務の性質と再建の可能性
債務の性質も、法的再生と私的再生の選択に影響を与えます。法的再生は、債務の一部を免除したり、債務の支払い条件を変更したりすることが可能です。一方、私的再生では、債権者との交渉によって債務の返済計画を策定することが求められます。したがって、債務が多く、返済が困難な場合には、法的再生を選択することが有効です。一方、返済が可能な範囲での再建を目指す場合には、私的再生が適しています。
3)メリットとデメリットの比較と検討
法的再生と私的再生のメリットとデメリットを比較し、検討することも重要です。法的再生のメリットは、債務の免除や支払い条件の変更が可能であり、企業の再建が図れる点です。一方、デメリットとしては、裁判所の手続きによる経営権の制限や手続きの時間と費用がかかることが挙げられます。
私的再生のメリットは、迅速な再建が可能であり、経営権の保持ができる点です。しかし、債権者との交渉が難航する場合や、債務の返済計画が達成できない場合には、再建が困難となるデメリットもあります。
これらのメリット・デメリットを比較して、自社にとって適した再生方法を選択しましょう。ただし、これらの選択には法律・税務などさまざまな要素が関係し、非常に複雑です。まずは、専門家に相談し、アドバイスを受けながら検討することがおすすめです。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。
関連記事





